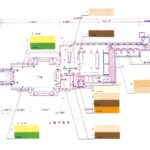まず、復原すべき色彩をどのように施工者に伝えるかということですが、新しい建物であれば日本塗料工業会が出している色見本帳等を利用することで、確実に施工者に伝達することができます。しかし、古い建物に用いられている色彩は、不思議なほどこの色見本帳と一致しません。色見本帳にある現代色と過去の色とは微妙な隔たりがあると言えるでしょう。
今回の色彩復原(注1)では、現場に残っている当初の色跡をできる限り広く露出させ、直接塗装業者にお願いして現場調合してもらいました。そして、和室の北端の壁を選び、色合せしたペンキを実際に塗って様子を見ました。油性ペンキ塗は最低でも3回は重ね塗りをしますので、下地塗の段階で実験したわけです。
そうした作業を何度か繰り返し、現場調合で得られた結果を基に工場で調合したペンキを塗ったのが現在の応接室や和室、廊下に見られる色彩です(※1)。ペンキの艶はそのままでは生々しいため、40パーセントほど落としてあります。こうした判断と結果については後世の評価を待ちたいと思いますが、私自身としては意外なほど違和感がないものになったのではないかと安堵しています。
- (※1) 今回採用した日本ペイントの油性調合ペイントについては、山邑邸の特色として同社内で記録に留められ、いつでも再現が可能になっています。
- (注1) 1995~1998年に足立教授が携わった災害復旧工事
最上階の食堂については、前回行われた保存修理(注2)の際に下地となる漆喰仕上げから塗り替えられており、竣工当初の壁のサンプルが保存されていませんでした。よって今回の修理では、前回の保存修理の際に採用された色彩を継承することにしました。おそらく同じ色彩であったろうという確信はありましたが、実際に証拠となる塗り色のサンプルが残っていない以上、その次に確実な前回の修理で採用された色彩を採用した訳です。食堂の色彩が他と比べると多少薄い茶褐色になっているのはそのためです。

今後、こうした修復の度に生じる差異を無くすために、今回の色彩復原では、次の修理の根拠となるサンプルの保存を心がけ、下地が剥離していないところはできるだけ残すように心がけました。そのために内部の壁をよく観察すると、表面にざらつきがあるものと無いものがあるのが分かります。ざらつきがある方が、下地からの修理が必要なために当初の漆喰壁を落とし、元々のテクスチュア(肌理)に復したところです。逆に平滑な壁の方は、竣工当初の下地やペンキを残すため、剥離しそうな部分だけを取り除いてペンキを塗り直したわけです。しかしやや平坦な印象はこの山邑邸の建設に携わった建築家の意図とは違ったものとなっているかもしれません。
- (注2) 1985~1988年に実施された保存修理工事
かつて構造の大家であった佐野利器(※2)は、建築とは色とか形といったことを問題にする婦女子の世界という印象をもち、構造家を志したといわれています。もちろん、建築の本質として色や形を抜きには語れませんし、現代建築のように装飾を用いなくなってからは、なおのこと色彩の重要性は高まっていると言えます。
この山邑邸の色彩を復原してみて、ル・コルビュジエのようなモダニスト達が大々的に用い始めたペンキ塗りという技法が、なぜ自然主義者であるライトの作品にあるのかという理由が少し理解できたように思われます。それはつまり、この素材の選択はライトではなく、遠藤新や南信といったもっと若い世代でなければできない判断であったということです。
- (※2) 1956年(昭和31年)生まれの建築構造学者。東京帝国大学建築学科を卒業後18年間同校教授を勤め、耐震構造学の基礎を築いた。
逆に、山邑邸の場合には、まずコンクリートの躯体にわざわざ漆喰を塗り、表面を少しざらざらしたテクスチュアにしてからペンキを塗っているところに前の時代からの継承を感じさせます。この山邑邸の後の一般的な鉄筋コンクリート造の仕上げとしては、プラスター塗り(※3)かモルタル塗り(※4)の上からペンキを塗るのが標準的な仕様になるのですが、砂漆喰塗りの柔らかい肌合いが選ばれているところは、ライトの弟子ならではの判断と言うべきでしょう。
山邑邸が完成した大正時代には、西洋館の内壁、天井の仕上げは漆喰塗りか壁紙張りくらいでした。ライトと親交があり、日本の住宅建築のパイオニアである武田五一(※5)も、芝川家住宅(※6)(現在は明治村に移築、明治45年建設)では土壁や色土壁を試みていたようです。明治村に芝川家住宅が移築された際に復原された玄関ホールの金色の真鍮粉塗りは昭和期の増築の際に改装されたものですので、明治末から大正期にかけて漆喰塗りに代わる新しい素材が求められていたと考えられます。また、少し後の昭和戦前期になると、先に触れたようにモダニズムの影響も現れ始めます。
そうした新しい選択と、ライトの技法の継承という二重性がこの山邑邸の素材の選択には現れているように思います。つまり、この建築は現代的な素材であるペンキを大々的に用いた、次の時代に繋がる実験的な作品であるとともに、ライトの素材感の余韻を残したものでもあるのです。
私は、これまでこの山邑邸に「垂直方向への空間展開」というライトの新境地が見いだせるのではないかと指摘してきましたが、このペンキという素材の選択についても歴史的な転機としての評価ができるのではないかと考えています。
- (※3) 鉱物質の粉末を、水で練り混ぜた塗り壁。
- (※4) セメントや砂、水を練り混ぜた壁
- (※5) 1872年(明治5年)生まれ。「関西建築界の父」とも言われ、近代日本を代表する建築家の一人。
- (※6) 大阪の商人 芝川又右衛門の別荘。愛知県の登録有形文化財に指定。
写真・図面・解説文 / 足立 裕司 氏